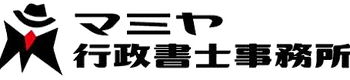任意後見制度と任意後見契約について行政書士が解説します
任意後見制度とは
任意後見制度は、将来、ご自身の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ選んだ人(任意後見人)に、生活や財産の管理などに関する事務を任せるための契約を締結しておく制度です。
この制度の最大の特長は、ご自身の意思を最大限に尊重できる点にあります。誰に、どのような支援を任せるかを、ご自身で自由に決めることができます。
法定後見制度との違い
任意後見制度と、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」との主な違いは以下の通りです。
任意後見制度の仕組みと流れ
契約の締結: 判断能力が十分にあるうちに、任意後見人となる人(任意後見受任者)と、公正証書で任意後見契約を結びます。
登記: 公証人が法務局で契約内容の登記を行います。これにより、契約の存在が公的に証明されます。
効力発生: 本人の判断能力が低下したら、本人や親族、または任意後見受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。
後見開始: 家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人が正式な役割を開始します。任意後見監督人は、任意後見人が適切に職務を行っているかを監督します。
メリットとデメリット
メリット
本人の意思を尊重できる: 任意後見人や、任せる事務の内容を自由に決められるため、将来の希望に沿った形で財産や生活の管理を任せることができます。
信頼できる人に任せられる: 裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度とは異なり、ご自身が心から信頼できる人に支援を依頼できます。
財産の管理範囲を限定できる: 契約で特定の財産のみ管理を任せるといった、柔軟な対応が可能です。
デメリット
取消権がない: 成年後見人、保佐人、補助人には、本人が単独でできない行為について取消権が認められています(民法9条、13条4項、17条4項)。これに対して、任意後見人には取消権が認められておらず、本人が独断で行った法律行為を取り消すことができません。その結果、本人の保護が不十分となる可能性があるので注意が必要です。
死後事務は対象外: 任意後見契約は本人の死亡によって終了するため、葬儀や埋葬、財産整理などの死後事務を任せることはできません。別途、死後事務委任契約が必要です。
任意後見監督人の報酬が発生する: 任意後見人が親族の場合でも、監督人への報酬は本人の財産から支払う必要があります。
任意後見契約とは
任意後見契約とは、将来自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に、自分の生活や財産の管理に関する事務を任せる契約のことです。
この契約は、本人の意思が尊重されることが大きな特徴であり、「法定後見制度」とは異なり、本人が元気なうちに、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を自由に決めることができます。
任意後見契約の特徴
本人の意思を尊重: 本人が、最も信頼できる人や専門家(親族、弁護士、司法書士、行政書士など)を任意後見人として選び、後見事務の内容(代理権の範囲)を具体的に定めます。これにより、ご自身の希望に沿った支援を受けることが可能になります。
契約の効力発生: 任意後見契約を締結した時点では、まだ効力は生じません。本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選任された時から効力が発生します。
公正証書での作成が必須: 任意後見契約は、必ず公証人が作成する公正証書によって行わなければなりません。これは、本人の意思を明確にし、契約内容の信頼性を確保するためです。
契約できる内容: 任意後見人に委任できる事務は、法律行為に限定されます。具体的には、預貯金の管理や不動産の売買、介護サービスなどの各種契約手続きなどが挙げられます。身の回りの世話や介護といった事実行為は含まれません。
任意後見契約の種類
契約を締結するタイミングや内容によって、主に以下の3つのタイプがあります。
将来型: 契約締結時は心身ともに健康で、将来の備えとして締結するものです。本人の判断能力が低下した後に、任意後見監督人が選任されて効力が発生します。
移行型: 任意後見契約と同時に、財産管理や見守りなどの「任意代理契約」を締結するものです。判断能力が低下する前から支援を受け、将来的に任意後見に移行することを目的とします。
即効型: 既に軽度の認知症などで判断能力が低下しているが、契約を締結する能力はまだある場合に、すぐに支援を開始できるよう締結するものです。契約締結後、速やかに任意後見監督人の選任を申し立てます。
任意後見契約は、将来の生活の安心を守るための有効な手段であり、特に身寄りのない方や、ご家族に負担をかけたくない方にとって有用な制度です。
行政書士に任意後見契約の作成を依頼する主なメリットは、専門知識に基づいたサポートを受けられること、ご自身の意向に沿った柔軟な契約を作成できること、そして将来のトラブルを回避できることです。
1. 専門的なサポートと総合的な提案
行政書士は、任意後見契約だけでなく、見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約など、関連する複数の契約について専門的な知識を持っています。これにより、ご自身の状況や希望に合わせて、将来の不安を包括的に解消するための最適なプランを提案してくれます。
2. 本人の意向を反映した柔軟な契約作成
依頼者のライフプランや希望を丁寧にヒアリングし、代理権の範囲を細かく設定するなど、オーダーメイドの契約書を作成できます。これにより、画一的なひな形ではなく、ご自身の意向を反映したきめ細かな後見計画を立てることが可能です。
3. 将来のトラブル回避
任意後見契約は公正証書で作成されるため、ご本人の意思が公的に証明され、契約内容の信頼性が高まります。これにより、将来、親族間での財産管理をめぐる争いを未然に防ぐ効果が期待できます。
4. 専門家が任意後見人になる選択肢
身近に信頼できる人がいない場合や、家族に負担をかけたくない場合、行政書士が任意後見人として就任してくれるケースもあります。これにより、安定した専門的なサポートを継続的に受けることが可能になります。
マミヤ行政書士事務所では、任意後見契約や死後事務委任契約についてサポートいたします。ご不安やお悩みの方は、マミヤ行政書士事務所までご相談ください。