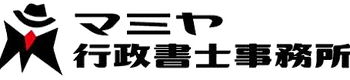危急時遺言を作成する方法と公正証書遺言を作成する重要性を解説します
「危急時遺言」とは、病気や事故などで死亡の危険が迫っている状況において、通常の方式による遺言を作成できない場合に認められる特別な遺言方式です。
危急時遺言の種類
危急時遺言には、以下の2種類があります。
1. 一般危急時遺言(民法976条)
要件
遺言者が病気や事故などで死亡の危険に瀕している
証人3人の立会いのもとで口頭で遺言をする
証人の1人が遺言の内容を筆記し、他の証人とともに署名押印する
遺言の筆記内容を遺言者および他の証人に読み聞かせ、確認する
遺言後20日以内に家庭裁判所で確認の手続きを行う(確認されないと無効)
2. 船舶遭難時遺言(民法977条)
要件
船舶が遭難していて、通常の遺言ができない
証人2人以上の立会いのもとで口頭で遺言をする
証人の1人が遺言の内容を筆記し、他の証人とともに署名押印する
20日以内に家庭裁判所で確認の手続きを行う
注意点
危急時遺言は一時的な措置であり、家庭裁判所の確認が必要
確認されなければ遺言は無効となる
可能であれば、事前に公正証書遺言を作成しておくのがベスト
危急時遺言をする必要があるケースは、遺言者が急激な体調悪化や事故などで死亡の危険が迫っており、通常の遺言を作成する余裕がない状況です。以下のようなケースが考えられます。
1. 突然の重病や手術前の状況
✅ 終末期の病気で意識があるが、公正証書遺言を作る時間がない
✅ 事故や急病で重篤な状態になり、今すぐ意思を伝えないと間に合わない
✅ 緊急手術を控えており、万が一の事態に備えたい
例:
・末期がんで余命が短く、入院中に財産を特定の家族に残したい
・心臓病で倒れ、意識があるうちに遺言をしたい
2. 事故や災害に巻き込まれた場合
✅ 災害(地震・津波・洪水など)に遭い、助かるかわからない状況
✅ 交通事故で重傷を負い、意識があるうちに遺言を残したい
例:
・飛行機事故で生存が危ぶまれる状況
・登山中に遭難し、救助が間に合わないかもしれない
3. 戦争やテロ、船舶の遭難
✅ 戦争地帯や紛争地域で命の危険がある
✅ 船が沈没する可能性があり、乗客や乗組員が遺言をしたい
例:
・戦地で活動中のジャーナリストや軍人が、急に身の危険を感じた
・クルーズ船が沈没しそうで、最後に家族へ財産を残したい
4. その他、緊急性の高い場合
✅ 海外滞在中に突然の病気になり、日本の公証役場で遺言を作成できない
✅ 認知症などの進行が早く、判断能力が失われる直前である
例:
・海外出張中に倒れ、日本の財産について遺言を急ぐ
・アルツハイマー型認知症と診断され、医師から数日で判断能力がなくなる可能性があると言われた
⚠ 注意点
口述による危急時遺言は20日以内に家庭裁判所の確認が必要(これをしないと無効となる)
証人が3人以上必要(船舶遭難時は2人)
可能であれば、事前に公正証書遺言を作成する方が確実です。
💡 事前の備えが大切です。危急時遺言が必要になる前に、早めに遺言書の準備をしておきましょう。
危急時遺言と公正証書遺言には、大きな違いがあります。以下の表で比較しながら解説します。
| 項目 | 危急時遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 目的 | 死亡の危険が迫っている緊急時に作成 | 健康なうちに確実な遺言を残す |
| 作成できる状況 | 病気・事故・災害などで急な危険があるとき | いつでも作成可能 |
| 手続き | 口述で証人に伝え、証人が筆記 | 公証人が遺言者の口述を筆記 |
| 証人の人数 | 3人以上(船舶遭難時は2人以上) | 2人以上 |
| 公証人の関与 | なし(証人のみ) | 公証人が作成・保管 |
| 有効性の確定 | 20日以内に家庭裁判所の確認が必要 | 作成時点で法的に有効 |
| 紛失・偽造のリスク | 高い(証人が筆記し保管するため) | なし(公証役場が原本を保管) |
| 費用 | 基本的に無料(証人の手配費用などは別途発生) | 有料(財産額によって公証人手数料が変動) |
危急時遺言はあくまで緊急を要する場合にのみ利用される制度になります。
できることならば、事前に公正証書遺言を作成されることをお勧めします。
マミヤ行政書士事務所では公正証書遺言や自筆証書遺言、危急時遺言のご相談を承っております。
お悩みの方ははまずはマミヤ行政書士事務所までご相談ください。