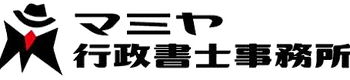M&A、事業承継の支援について解説します
M&A(企業の合併・買収)や事業承継(後継者への事業の引継ぎ)は、経営者にとって大きな決断であり、法務面、税務面など多岐にわたる手続きが必要となります。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や提出代行の専門家として、主に法務面で経営者をサポートします。
行政書士が支援するM&Aと事業承継の主な業務
行政書士がM&Aや事業承継で提供する主な支援内容は、以下の通りです。
①事業承継計画の策定支援:
経営者の意向や会社の現状をヒアリングし、事業の引き継ぎ方法(親族内承継、従業員承継、M&Aなど)を検討します。また、具体的なスケジュールや必要な手続きを整理し、スムーズな承継計画の策定をサポートします。
②契約書等の作成:
事業譲渡契約書、株式譲渡契約書、合併契約書など、M&Aや事業承継の過程で必要となる様々な契約書の作成をサポートします。これにより、法的トラブルを未然に防ぎ、当事者間の合意を明確にします。
③許認可手続きの代行:
建設業、飲食業、運送業、介護事業など、特定の事業を行うには、官公署の許認可が必要です。M&Aや事業承継によって事業主体が変わる場合、許認可の名義変更や新たな申請が必要になります。行政書士は、これらの複雑な手続きを代行し、事業が滞りなく継続できるよう支援します。
④補助金申請のサポート:
事業承継やM&Aには、国や自治体の補助金が活用できる場合があります。行政書士は、これらの補助金の情報提供から、申請に必要な書類作成までを支援し、経営者の費用負担軽減に貢献します。
⑤他士業との連携:
行政書士の業務範囲は法務書類の作成が中心です。そのため、M&Aや事業承継を総合的に支援するには、税理士(税務)、司法書士(登記)、弁護士(訴訟・交渉)など、他の専門家と連携して課題解決にあたります。行政書士は、これらの専門家との連携窓口としての役割も担い、経営者がワンストップで相談できる体制を構築します。
M&Aや事業承継は、経営者の人生にとって大きな転機です。行政書士は、単なる手続き代行業者ではなく、経営者の想いやビジョンを深く理解し、寄り添いながら、円滑な事業の引き継ぎを支援するパートナーと言えるでしょう。
デューデリジェンスとは、Due(当然の、正当な)、Diligence(精励、努力)という意味で、略して「DD(ディーディー)と呼ぶこともあります。
具体的には、M&Aや組織再編、企業再生を行う際に、対象企業の事業内容や資産・負債を調査・確認し、財務や法務等の面から企業を分析する行為です。
特に、M&Aでは買手企業が専門家に依頼し、譲渡対象企業の業種や状況に応じて、様々な切り口から調査を行ないます。
一口にDDと言っても、
・ビジネス(事業)DD
・税務・財務DD
・法務DD
・労務(人事)DD
・環境(特に不動産)DD 等様々です。
珍しいところでは、医療機関に対する、レセプトを精査するDDといったものもあります。
このように多種多様な切り口のDDがありますが、目的を持たずに闇雲に実施していたのでは時間もコストも際限なくかかります。目的を絞り込み、リスクが表面化した場合のヘッジ方法を検討し、費用対効果を考えて、何をやるのかではなく、何をやらないのかを決めていくことが大切です。
税務・財務に関するDDは、譲渡側顧問税理士との連携がきちんと取れれば最終契約書の表明保証に留め、コストを掛けないというケースもあります。
譲渡対価が億を超えるようなM&Aであれば、DDのコスト割合は小さいかもしれませんが、数百万のM&Aであれば、ケースにもよりますがDD費用の方が高額になってしまうことだって考えられます。
M&Aにはさまざまな手法があり、目的や会社の状況によって使い分けることが重要です。ここでは、M&Aの主な方法について解説します。
株式譲渡
売り手企業の株式を買い手企業が取得し、子会社化、または完全子会社化する最も一般的な手法です。
メリット: 手続きが比較的簡単で、短期間で実行できる。経営権や資産、負債などを包括的に引き継げる。
デメリット: 簿外債務(貸借対照表に記載されていない債務)や偶発債務(将来発生するかもしれない債務)を引き継いでしまうリスクがある。
事業譲渡
売り手企業の事業の一部または全部を、個別に選んで買い取る手法です。
メリット: 必要な事業だけを選んで取得できるため、不要な資産や負債を引き継ぐリスクを避けられる。
デメリット: 資産や負債、契約などを個別に引き継ぐ手続きが必要で、手間がかかる。また、従業員の雇用契約も個別に結び直す必要がある。
第三者割当増資
売り手企業が新株を発行し、買い手企業がその新株を引き受けることで経営権を取得する手法です。
メリット: 売り手企業は資金調達ができる。また、買い手企業は比較的少ない資金で経営権を得られる場合がある。
デメリット: 既存株主の持ち株比率が低下するため、事前の調整が不可欠。
吸収合併
一方の会社(存続会社)が、もう一方の会社(消滅会社)の権利義務をすべて引き継ぎ、消滅会社は解散します。
メリット: 手続きが比較的スムーズで、消滅会社の権利義務を包括的に承継できるため、個別の手続きが不要。
デメリット: 消滅会社の資産だけでなく、負債や偶発債務などもすべて引き継ぐ必要がある。
新設合併
合併するすべての会社が解散し、新たに設立した会社がすべての権利義務を引き継ぎます。
メリット: 新しい会社でゼロから組織体制を構築できる。
デメリット: すべての会社が解散するため、許認可などを新たに取得する必要があり、手続きが複雑で時間もかかる。
株式交換
買い手企業が自社株式を対価として、売り手企業の全株式を取得し、完全親子関係を構築する手法です。
メリット: 現金を使わずにM&Aを実行できる。
デメリット: 買い手企業が非上場の場合、売り手企業の株主にとって、換金が難しい株式を保有することになる。
株式移転
既存の会社が発行済み株式のすべてを、新たに設立する会社に取得させる手法です。主に、ホールディングス体制(持株会社体制)への移行で用いられます。
メリット: 複数の会社が共同で持株会社を設立できる。
デメリット: 新会社設立の手続きが必要となる。
どの手法を選ぶかは、M&Aの目的や事業の状況、将来的なビジョンによって異なります。専門家と相談しながら、最適な方法を検討することをおすすめします。
M&Aの買い手(バイサイド)は、M&Aを成功させるために様々な点に注意する必要があります。特に重要なのは、リスクを徹底的に洗い出し、買収後の統合(PMI)までを見据えた戦略を立てることです。
以下に、バイサイドが気を付けるべき主なポイントをまとめました。
1. 目的の明確化と戦略策定
M&Aの成功は、買収後のシナジー効果の実現にかかっています。そのため、まず「なぜこの会社を買収するのか」という目的を明確にすることが不可欠です。
買収目的の明確化:
新規事業への参入
既存事業の拡大(市場シェアの拡大)
技術やノウハウ、ブランドの獲得
優秀な人材の確保
コスト削減(生産・物流の効率化など)
買収対象の選定:
目的を達成するために最適な会社はどこか、譲渡企業(売り手)の事業内容、財務状況、市場での競争力などを多角的に評価する。
自社の既存事業との相性やシナジー効果の可能性を十分に検討する。
2. デューデリジェンス(DD)の徹底
デューデリジェンス(買収監査)は、M&Aにおける最大の失敗要因である「想定外のリスク」を避けるために最も重要なプロセスです。買い手は、売り手から提供される情報だけでなく、専門家を交えて多角的に調査を行います。
財務デューデリジェンス:
貸借対照表に記載されていない「簿外債務」(退職金、未払い残業代など)や「偶発債務」(訴訟リスクなど)の有無を徹底的に確認する。
粉飾決算や不正経理がないかを調査する。
財務状況が事業の実態を正確に反映しているかを確認する。
法務デューデリジェンス:
契約上の問題(有利な契約が買収後に解除される可能性はないか)やコンプライアンス違反、過去の訴訟リスクなどを調査する。
許認可や特許、知的財産権の状況を確認する。
事業デューデリジェンス:
事業の将来性、市場における競争優位性、収益構造などを評価する。
買収後に想定しているシナジー効果が本当に実現可能か、事業計画の妥当性を検証する。
人事デューデリジェンス:
従業員の雇用条件や退職金制度、労働組合の有無、離職リスクなどを調査する。
特にキーマン(経営者や優秀な技術者、営業担当者など)が買収後に離職しないか、引き止め策を検討する。
3. 適正な企業価値評価(バリュエーション)
M&Aの買収価格は、デューデリジェンスの結果に基づいて交渉されます。売り手の言い値を鵜呑みにせず、客観的なデータに基づいた適正な価値評価が不可欠です。
高値掴みの回避:
買収への強い思い込みや感情的な決断は、相場よりも高い価格での買収につながるリスクがある。
事業の将来性やリスクを冷静に評価し、投資対効果が見合うか慎重に判断する。
4. 買収後の統合プロセス(PMI)
M&Aの成約はゴールではなく、スタートです。買収後に両社がスムーズに統合し、シナジー効果を最大化するための計画(PMI:Post Merger Integration)を事前に策定しておくことが重要です。
企業文化の統合:
M&Aが失敗する大きな原因の一つが、異なる企業文化や風土の衝突です。買収後、新しい組織としてのビジョンや行動規範を共有し、コミュニケーションを密にすることで、従業員のモチベーション低下や離職を防ぐ。
組織・システム統合:
人事制度や経理システム、ITインフラなどを円滑に統合する計画を立てる。
誰が新しい組織のリーダーシップを担うか、責任の所在を明確にする。
5. 情報管理と専門家の活用
M&Aの交渉過程で、情報漏洩は致命的なリスクとなります。また、複雑なプロセスを円滑に進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。
情報漏洩の防止:
秘密保持契約(NDA)の締結はもちろん、M&Aの情報を扱う担当者を限定し、厳重な情報管理体制を構築する。
専門家の活用:
M&A仲介会社、金融機関、公認会計士、弁護士など、それぞれの分野の専門家と連携することで、リスクを最小限に抑え、交渉を有利に進めることができる。
これらのポイントを念頭に置き、慎重かつ戦略的にM&Aを進めることが、バイサイドの成功に繋がります。
M&Aや事業承継でお悩みのかたは、マミヤ行政書士事務所までご相談ください。