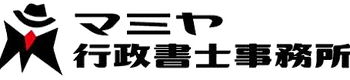遺言書があっても紛争になるケースとは。笑顔相続にする方法を解説します
公正証書遺言があっても紛争になる相続は、複数のケースが考えられます。公正証書遺言は高い証拠能力を持ち、原則として有効性が争われることは少ないですが、それでも以下のケースでは紛争に発展する可能性があります。
1. 遺留分を侵害している場合
「遺留分」という配偶者や子供といった一定の相続人に、最低限の遺産相続を求めることができる権利を認めています。公正証書遺言で特定の相続人や第三者に全財産を遺贈する旨が記載されていても、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、財産を受け取った人に対して金銭の支払いを求めることができます。
この請求は、多くの場合、当事者間の話し合いで解決しない場合、調停や訴訟に発展します。
2. 遺言内容が不明確、または解釈が分かれる場合
公正証書遺言は公証人が作成するため、通常は明確な表現が用いられます。しかし、それでも以下のようなケースで解釈の余地が生じ、紛争になることがあります。
財産の特定が曖昧: 「〇〇の土地」と記載されていても、登記簿上の地番と異なるなど、どの土地を指すのか不明確な場合。
表現の多義性: 特定の文言が複数の意味に解釈できる場合。
特定の財産の変動: 遺言作成後に記載された財産が売却されたり、別の財産に変わったりした場合、その新しい財産が遺贈の対象となるのか否か。
3. 遺言能力の有無が争われる場合
公正証書遺言作成時、公証人は遺言者の意思能力を確認しますが、それでも後になって、遺言者が認知症などで行為能力を欠いていたと主張されるケースがあります。
特に、遺言作成時の健康状態や精神状態について、医師の診断書や介護記録などを基に争われることがあります。
4. 詐欺や強迫によって作成されたと主張される場合
遺言者が誰かに騙されたり、脅されたりして遺言を作成したと主張されるケースです。
公正証書遺言の場合、公証人が立ち会っているため、このような主張が認められるのは非常に稀ですが、全くないわけではありません。
5. 遺言書に記載されていない財産がある場合
遺言書に全ての財産が記載されていない場合、記載されていない財産については法定相続分に基づいて分割することになります。
この未記載財産の範囲や評価について、相続人間で意見が対立し、紛争になることがあります。
6. 特定の相続人が遺言内容に不満がある場合(感情的な対立)
法的には有効な遺言であっても、特定の相続人が遺言内容に納得できず、感情的な対立から紛争に発展することがあります。
「親は自分に冷たく、他の兄弟には優しかった」といった過去の経緯や、生前の貢献度など、感情的な側面が複雑に絡み合い、解決を困難にする場合があります。
7. 遺言執行者の選任や職務に疑義がある場合
遺言執行者が選任されている場合でも、その選任自体に問題があったり、遺言執行者が適切に職務を遂行していないと主張されたりするケースです。
公正証書遺言があっても紛争を避けるための対策
遺留分に配慮した遺言内容にする: 遺留分を侵害する可能性がある場合は、その旨を明記し、遺留分侵害額請求に対する準備を促す文言を入れるなど、紛争を未然に防ぐ配慮が重要です。
財産内容を明確に特定する: 不動産は登記簿通り、預貯金は金融機関名・口座番号など、具体的に特定すること。
付言事項で意思を伝える: なぜそのような遺言内容にしたのか、相続人への感謝や配慮の言葉などを付言事項として記載することで、相続人の感情的な納得感を促すことができます。
専門家に相談する: 遺言作成前に行政書士などの専門家に相談し、潜在的な紛争リスクを洗い出し、対策を講じることが最も重要です。
公正証書遺言はそれだけで全ての紛争が回避できるわけではありません。相続人それぞれの事情や感情を考慮し、専門家のアドバイスを基に、より円満な相続を目指すことが肝要です。
笑顔相続を実現するための秘訣は多岐にわたりますが、最も重要なのは「事前の準備」と「相続人同士のコミュニケーション」に尽きます。以下に具体的なポイントを挙げます。
1. 生前の準備を徹底する
遺言書の作成(やはり公正証書遺言がベスト):
誰に何をどれだけ残したいか、明確な意思表示をします。法定相続分にとらわれず、特定の相続人への配慮や、お世話になった人への遺贈なども可能です。
遺留分への配慮は必須です。遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求によりトラブルになる可能性があります。専門家と相談し、遺留分を考慮した内容にすることが重要です。
なぜそのように財産を分けるのか、相続人への感謝やメッセージを付言事項として記載すると、感情的な納得感を促し、紛争を防ぐ効果があります。
特定の財産を特定の相続人へ、という場合は、代償分割(不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金を渡す)の用意なども検討し、遺言書に記載しておくと良いでしょう。
財産内容の把握と整理:
預貯金、不動産、有価証券、保険、借金など、すべての財産をリストアップし、所在や評価額を明確にします。
エンディングノートなどを活用して、財産目録を作成し、相続人がアクセスしやすいようにしておくと良いでしょう。
不動産など分割しにくい財産は、売却して現金化したり、複数所有しておくことで、分割を容易にすることも検討します。
生前贈与の活用:
計画的に生前贈与を行うことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。年間110万円までの基礎控除を活用するなど、非課税枠の範囲内で少しずつ贈与することも有効です。
贈与は、トラブルの元にならないよう、贈与を受けた財産の使途や意図を明確にしておくことが大切です。
相続税の試算と納税資金の確保:
相続税が発生するかどうか、どのくらいの税額になるかを試算し、納税資金を確保する準備をしておきます。
生命保険を納税資金の準備として活用するのも有効な手段です。
2. 相続人とのコミュニケーションを密にする
家族会議の開催:
生前の元気なうちに、家族で相続について話し合う機会を持つことも重要です。
それぞれの相続人の考えや希望を共有し、お互いの状況を理解し合うことで、不満や誤解が生じるのを防ぎます。
親の介護や看病をしてくれた相続人への配慮など、感情的な側面も共有し、感謝の気持ちを伝えることが、円満な相続につながります。
情報の透明性を保つ:
財産の内容や遺言書の内容について、特定の相続人だけに情報を開示せず、相続人全員に平等に情報を提供することが大切です。
不信感はトラブルの大きな原因となるため、「秘密は極力避ける」ことが笑顔相続の秘訣です。
親の意向を伝える:
遺言書の内容も含め、なぜそのように財産を分けるのか、親自身の考えや気持ちを伝えることで、相続人は納得しやすくなります。
もし親が直接伝えにくい場合は、遺言書にその旨を詳細に記載することも有効です。
3. 専門家のサポートを活用する
弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家へ相談:
相続は法律、税金、不動産など専門的な知識が必要となるため、早い段階で専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
遺言書の作成、遺産分割協議、相続税対策など、それぞれの専門家が適切なサポートを提供してくれます。
相続人間の調整が難しい場合や、感情的な対立が生じた場合にも、第三者である専門家が間に入ることで、冷静な話し合いを促し、解決へと導くことができます。
4. 感情に流されず、冷静な対応を心がける
相続は、故人を失った悲しみの中で行われるため、感情的になりやすいものです。
しかし、感情的な対立は、より複雑な紛争へと発展する可能性が高いため、冷静に話し合いを進めることが大切です。
法定相続分に固執せず、それぞれの相続人の事情を考慮し、柔軟な解決策を模索する姿勢も重要です。
笑顔続の究極の秘訣は、「相続人同士がお互いを理解し、尊重し、譲り合う気持ちを持つこと」と言われます。そのためには、故人(被相続人)が愛情と配慮をもって生前準備を行い、残された家族が協力し合う姿勢が不可欠です。
上記の内容はあくまで一例にすぎません。そのご家族ごとによってケースが違うため、そのご家族ごとの相続に対する準備や心構えが必要となります。ご不安なことがあれば、間を置かずに専門家にご相談されることをお勧めします。
遺言書の作成や、遺産分割、死後事務委任など相続に関するご相談は、マミヤ行政書士事務所までご相談ください。
事前のご予約で、土曜日・日曜日・祝日・夜間も対応いたします。